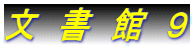
|
||||||||
 |
「幽 斎 殿 Ⅱ」 |
|
無限とは限りあるものが無いこと、すなわち個我すなわち自我なるものは無いことである。無我なることが無限なることであるのである。 自分すなわち自我は無く、神なること、渾(す)べての渾べてなることが無限なることなのである。自我の反対存在はただ一つなること、渾べての渾べてなることであるのである。渾べての渾べてでないことが自我なることであり、有限なることであるのである。 有限なるもの、個我なるものは無いのである。その無も無く、ただただ渾(す)べての渾べてなるもののみであることが無我なること無限なることであるのである。 “私は無いんですよ”と輝かれた時、大聖師は渾(す)べての渾べてなるよろこびをよろこび続けてい給うたのである。そのよろこびが聖歌歌詞の「満ち足りて欠くることなく 行くところさわりにあわず とこしえに悩むことなし」となってい給うのである。 自分は無い、ということは何故にうれしいのであるか。それは、自分は無いということが無限ということであり、渾(す)べての渾べてであるからなのである。渾べての渾べてなるもののみが實在であるのである。 「神の国は汝らの内にあり」とは、自分、自我という外なるものは無く、内のみ、渾べての渾べてであることなのである。 今日一日を渾(す)べての渾べてなるもののよろこびをもって生きよう。 『心』は宇宙に満つる實質、 と聖経『甘露の法雨』には書かれているのである。 この『心』こそ、満ち足りて欠くることなきもの、すなわち渾べての渾べてなるものなのである。 宇宙に満ちて欠けざるものを『心』と言い、「全能」と言い、神というのである。 吾れは無く、宇宙に満つる實質なる『心』のみが渾べての渾べてなのである。 自分の心で渾べての渾べてなるものを把えるのではないのである。自分の心は無い、と自分の心みづからがみづからの無を知って、無に消えることが、渾べての渾べてなるものが渾べての渾べてである實相がまる出しとなり、裸となることなのである。 渾べての渾べてなるものにおいては、知るものと知られるものとの相対は無いのである。渾べての渾べてなるものは独在であり、在りて在る今なのである。そして、その今なる實相(もの)こそまことの自分なるものなのである。 “吾れは感謝の本源である”という渾(す)べての渾べてなるものの声の、内より湧き出づるを憶(おぼ)えた今朝である。 本源なるもの、はじめのはじめにして渾べての渾べてなるもののみが在るのである。 吾れは無く、渾べての渾べてなるもののよろこびのみが在るのである。 この渾べての渾べてなるもののよろこびが本源なるもののよろこびであり、感謝なるものの本源であるのである。 何故に、不完全なるものは實在に非ず、なのであるか。不完全なるものは渾(す)べての渾べてなるものではないからなのである。 宇宙に満ちて欠けざる絶対なるものではない、即ちそれは自我なるものであるからなのである。 自分は無く、渾べての渾べてなるもののみが渾べての渾べてしているとき、そこに自然(じねん)、天然(てんねん)、法然(ほうねん)に輝き出でているのが個性というものなのである。 自分が無いとき、個性が現前しているのである。 自分が無いという渾べての渾べてなるもののよろこびが鳴っているのが「招神歌(かみよびうた)」であり、「大調和の神示」であるのである。 天国極楽浄土なる實相が文字となって輝き出でて「招神歌」となり、「大調和の神示」となり、聖典聖経となっているのである。 そのものが自分なき渾べての渾べてであるとき、それを“光り”というのである。 自分が無いときに観られる全べてを“光り”というのである。自分無きこと、すなわち無限なることが渾べての渾べてであるからである。 自分無きことが神想観において「ジーッと観わたすんですね」と尊師の言われる「ジーッと」の消息なのである。その消息において「全身の細胞ことごとく如意宝珠(にょいほうじゅ)にして渾べての渾べてなり」と観ずるのである。 一切を否定し、その否定をも否定したところを“今”といい、“ここ”というのである。そして“吾れ”というのである。 それが神想観における“吾れ、今、ここ”ということなのである。 一切を否定し、その否定をも否定したところを“渾べての渾べて”というのであり、それが實相であり、龍宮本源であり、高天原(たかあまはら)であるのであり、それが神の国であり、天国であり、極楽浄土であるのである。このことを受くることが“無の門関”に坐するということなのである。 やはり肉体の死を恐れるということは、實相のよろこびを発見できていないからにすぎないのである。 欠くることなき渾べての渾べてであり、完全なるものそのものである實相は不滅であり、今ここにあり、霊々妙々であるのである。實相だけでよいのである。神だけでよいのである。 實相は無限のよろこびであるのに、それ以外の何ものを求める必要があるであろうか。實相以外の何ものかを求めるのは實相を知らないにすぎないのである。 全實在宇宙がイザナギの大神そのものであることの現成(げんじょう)そのものが宇宙が浄まることであるのである。 全宇宙が住吉大神(すみよしのおおみかみ)(塩椎大神)(しおつちのおおみかみ)そのものであること。そしてイザナギの大神の宇宙浄めの御働きが住吉の大神となってあらわれ給うているのであるから、住吉大神はイザナギの大神とひとつであるが故に、イザナギの大神が全宇宙となって独神(ひとりがみ)していることを顕わすのがイザナギの大神のみそぎなるものの現成なのである。 内なる光りとは独神すなわち絶対神なるものの光りであるのである。 内とは独在なるもの、独尊なるものそのものをいうのである。独在とは在りて在るところのそれ自身存在そのものである相(すがた)であるのである。ひとり神は独在であり、渾べての渾べてであるが故に、身(みみ)を隠し給うているのである。隠れ給うているということは、それ以外からそれを観るところの、それと相対しているものが無いということであるのである。ただただ、在るものだけがひろびろと在りて在るのみなのである。それが實相界の弥廣殿(いやひろどの)なる相であるのである。 神想観の“はるばると目路の限り眺むるに十方世界ことごとく神なり”ということが独神(ひとりがみ)のひとりがみしている、神それ自身の鳴りひびきであるよろこびの相(すがた)であるのである。 萬物は同根であり、一つである。 それはどのような状態であるかを、現象のすがたから予想することは出来ない「一つなるもの」なのである。 一つであり一つであるところの証明不要の在りて在る荘厳存在であるのである。 ただただ「一つ」であるのであり、この一つから一切は展開してるのであるから、展開された側からもとの一つなるものを証明するということは有り得ないことであり、不必要なことなのである。 一切を超えるとは、自分を超えることにほかならなかったのである。 一切を超えることは「一つに切る」こと、現象を切って一つなる實相に至ること、そのことを超えることにほかならなかったのである。 今ここなる荘厳とは自分を超えている、自分ならざる自分が實在なる荘厳を生んでいることなのであった。 かくして、吾が内に無限、絶対、渾べての渾べてなるものを観じ、拝し、生み出しているのが荘厳なる吾れの吾れなるものであることを知るのである。 最早や吾れの吾れではないのである。荘厳そのものであるのである。 “最早や吾れ生くるに非ず、神の無限の生かすちからここにありて生き給うのである”。“神の生かすちから”とは生み出すはたらきそのものであり、その生み出しの力がここにありて渾べての渾べてであることなのである。 最早や自分はなく“生かす力” “生み出す力”のみ渾べての渾べてであるのである。自分はなく、生かすはたらきのみがここに渾べての渾べてであるのである。 すべてを生むもののみ、ここにあるのである。それ故に“私自身を生むもの”であるのがここにあり、實相を生むもの、龍宮本源を生むもの、高天原を生み、独神(ひとりがみ)なる七柱の神を生み出しているもののみ、ここにありて生み給うのである。 まことにも「カミムスビの神」とは、神を生むはたらき、絶対なるものを生む御はたらきそのものであり給う神であるのである。 “現象を否定しつくしたあとはどうなるのか”そこからが全托であるのである。どうなろうとこうなろうと無いものは無いのが真理であるのである。捨てて捨てて死ぬなら死んでもよいのである。そこに全托なるものがみづから生きているのである。生きものとしての全托なるものがここにあり給うのである。 全托なるものは全べてであり、全べての全べてであり、全べてなるものが生きて、在りて在るすがたが全托なるものなのである。 全托なるものはみづから生きているのであり、全べての全べてであるのである。 まことにもコトバは神であり給い、コトバは神をも生むのである。この相(すがた)がカミムスビであるのである。 一切の発せられるコトバは神であり、神が発し、神が発せられている相であるのである。 コトバがコトバを生み、神が神を生むのである。そして、そのコトバは自分自身なのである。 “無色透明”とは、ひとつなること、はじめのはじめなること、今ということであり、渾べての渾べてということである。 高天原も無色透明であれば、七柱の独神(ひとりがみ)も身(みみ)を隠し給う幽の幽なる無色透明にましますのである。 ひとつであるとは無色透明であることなのである。 浄まるとはひとつなる無色透明の輝きが更に勢(きよ)まること、生長することを意味しているのである。 “元津霊(もとつみたま)ゆ、幸(さき)はえ給え”とは、元そのもの、ひとつなること、渾べての渾べてなること、本源そのものを幸はえ給えということであり、本源なる澄み切りに澄み切らせ給えということなのである。 ひとつとは無色透明であり、澄み切りということなのである。それは今ここに久遠なるものとして如何なるものとも罜礙(けいげ)せず、渾べての渾べてであるのである。 目無堅間(めなしかつま)とは無色透明なるひとつなる渾べての渾べてなる澄み切りを意味しているのである。 澄み切りなるかな。澄み切りなるかな。ひとつなるかな。ひとつなるかな。 真空妙有とは澄み切りなるひとつなる創造の本源なる澄み切りの澄み切りであるのである。 基本的神想観において、自分が無色透明となっていることに感謝するのは、ひとつなる澄み切りの消息であるのである。 ひとつとは中心なる渾べての渾べてを意味しているのである。至大無外(しだいむがい)、至小無内(ししょうむない)の消息である。 神が一切のものを造り給うや 粘土を用い給わず、 木材を用い給わず、 槌(つち)を用い給わず、 鑿(のみ)を用い給わず、 如何なる道具も材料も用い給わず 粘土も木材も槌も鑿も道具も材料も“無い”のである。 これらのものは既に造られたるものである。造られたるものは、はじめのはじめから在ったものではなく“無い”のである。 神は“両親”を材料として吾れを造り給い、生み給うたのではないのである。 神は如何なる現象の世界の中のものをも材料として吾れを造り給い、生み給うたのではないのである。 神ご自身もまた吾れを造り給い、生み給うたところの原因、材料であり給うことは無いのである。 因縁そのものもまた神が吾れを造り給い、生み給う材料ではないのである。 神は造り給うことも生み給うこともないのである。神ご自身が造られ給うたのではなく、生み出され給うたものであり給わないのである。 すべての實在(まことの存在)は造られたるものではなく、生み出されたるものではないところの“在りて在る”存在なのである。 大聖師谷口雅春先生は如何なる道具も材料も(時間、空間も)用い給わずして聖典を現成し給うているのである。 人間は幸せになるための如何なる道具も材料も要らないのである。 内に常楽の国土を自覚してのみ 外に常楽の国土はその映しとして顕現せん。 とは“内だけでよい”と言える時においてのみ、常楽なるものがあることであり、映しの世界は全くの無関係となった時にのみ、常楽なるもののみがありつづけているのであり、何処にも映しの世界の存在はないのである。常楽とは内のみ、實相のみの消息であるのである。 自在説法ということは、説法は無いということである。 未だかつて生れたることなく、未だかつて悟りたることなく、未だかつて説法したることなき、それらと全く無関係の、無の無の無なる活気凛々(りんりん)たる輝くもののみ常楽しているのである。 三界に身を現さず。三界は無いのである。未だかつて来たるものなく、去って去りたるものなく、過去、現在、未来にあらず、過去、現在、未来そのものが無いのである。未だかつてどの時点においても説法せず。これが自在なる説法であるのである。 非雑食身(ひぞうじきしん)。非雑行身(ひぞうぎょうしん)。非説法身(ひせっぽうしん)である。 無の門関想うべし。無の門関透(とお)るべし。 無の無なる、それ自身渾べての渾べてであり、相対なきものこそ“立ついのち”であるのである。 独り子とは独り神ということであるのである。 独り子とは絶対なる子ということである。親があってはじめて子である、という因縁、相対の存在ではないということである。それ自身、在りて在る、渾べての渾べてなる独在なる子であるのである。 釈尊、キリストは一行も文章はお書きにならなかったのである。説法そのものが無いということを生きてい給うたのである。 神もまた一行も文章はお書きになっていないのであった。説法そのものが無いことそのことを生き給うてい給うのである。 その釈尊、キリストを無しとして超え給うているのが大聖師であり給うのである。 大聖師は“私は無い”と、生れたること無きご自分を生き給うたのである。説法は無いということは自分そのものが無いということを生き給うていることそのことなのである。その上に立って大聖師は自在に文章を書き給うたのである。 自在とは“無い”ということそのことであるのである。無の門関の消息である。 真空妙有、真空の生活が今を生きるということであるのである。 生れたる自分はなく、生れたる説法は無く、生れたる文章も無いのである。真空であり、澄み切りであるのである。 澄み切りとは、はじめのはじめであり、渾べての渾べてということであるのである。今ということである。 一切が無いということは、一切があるということであるのである。 無の門関とは一切がある門関であるのである。 一切があるからこそ、一切現象は無いのである。 吾が内に神あり。 神の内に吾れあり。 神は吾れに宣(の)り給う。 「吾れは汝を生み、汝は吾れを生めり」と。 「吾れは汝より生れたり」と。 吾れは如来の合掌の内にあり。 そして如来は宣り給う。 「吾れは汝より生れたり」と。 天地一切萬物ことごとくは、観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)すなわち尽十方無礙光如来(じんじっぽうむげこうにょらい)であり、その合掌の内に吾れあり、そして観世音菩薩は吾れに宣り給う。 「吾れは汝より生れたり」と。 高天原も、龍宮本源も、全實在界も、神詰(つま)りに詰り給う大神もすべて、吾れはその内に抱かれ、そして吾れに語りかけ給うのである。 「吾れは汝より生れたり」と。 コトバ(または思念)において、“無い”と言える全べてを“無い”とし、その“無い”も“無し”とすることこそ全身全霊浄まることにほかならないのである。 この浄まりを勢(きよ)まることの一筋の道があるのみであり、それのみでよいのである。 この浄まりの極(きわみ)において、浄まりなるものそのものが、手の舞い足の踏むところを知らないよろこびを輝き輝いて、一切の聖典のみコトバとなっているのである。 吾が内の内なる神の国そのものが鳴りひびいて、輝きわたって聖典となり、聖経となり、天地一切萬物となって輝きわたり、鳴りわたっているのである。 天地一切は吾れの吾れなるものの鳴り出でであり、輝き出でであるのである。 その相(すがた)が天地一切萬事萬象萬物ことごとくが観世音菩薩すなわち尽十方放射なる無礙光なる如来であることなのである。 それが宇宙の大神イザナギの命(みこと)が住吉大神となり給いて、光明燦然(さんぜん)として宇宙を輝いてい給う相であり給うことなのである。 實相なるものは一切を放っているのである。實相は満ちて欠けざるが故にである。満ちて欠けざるが故に、外に求める必要はないのである。求める必要のない存在はただただ創造し、表現するのみである。 實相なるもの、円満なるものは、外なるものを求めることを断ち切るという相(すがた)ではないのである。一切を円満しているが故に、求めること自体が不要、すなわち無いのである。 浦島太郎が龍宮界において、たった一人男性としてあるということは“一人児(ひとりご)”であることを意味しているのである。すなわち自分をとり巻く全べての全べてが天照大御神(すなわち女性なるもの、如性なるもの)であることを意味しているのである。 神我一体、萬物同根は本来因そのものの相(すがた)であって、他の如何なる因縁たるものでもないのである。本来因なるものそのものが渾べての渾べてであるのである。即ち、“一つ”なるものそのものなのである。 神は如何なる必要性もなくして創造し給うているのである。 必要性によって意義づけされることなき相(すがた)こそが真の創造性であり、神の子の創造の相もまた同じ消息であるのである。 あらゆる出逢いと見ゆるものの相(すがた)の前に“一つ”なることが先きなのである。因縁仮和合(いんねんけわごう)を超えているまことの相であるのである。出逢いが無くとも“一つ”なるものは在りて在りつづけなのである。 親が先きか子が先きか。子のいない親はなく、親のいない子は無いのである。親と子とは“一つ”であるのである。 神なる親様が先きか、子なる神の子が先きか。神の子の無き親様は無く、親様の無き神の子は無いのである。 神と神の子は“一つ”なるものなのである。それは因縁仮和合の相(すがた)ではなく、本来因すなわち本来なる、はじめのはじめなる因(もと)そのものの、そのままの相によるが故に、久遠そのものであるのである。 それは如何なるものによっても影響左右されることなき、崩るることなき不滅なるものであるのである。はじめのはじめ、“一つ”なるものにつきて―――。 神と神の子は出逢いを必要としない“一つ”そのものであるのである。 “一つ”なるものの消息は、すなわち「大調和」の消息であり、「大調和の神示」は“一つ”なるものの鳴りひびき、輝きが言葉に翻訳されたるものなのである。“一つ”なる消息こそが、こらえ合ったり我慢し合ったりすることのない相(すがた)なのである。 “一つ”なるものは、外なる如何なるものによっても崩れ去ることは無いのである。死によってさえも離され崩されることはないのである。 出逢いという因縁仮和合によって成り立ったものは、他への出逢いまたはそのあり具合によって崩れるほかはないのである。出逢いによらないものが“一つ”なるものなのである。 神我一体 ・ 自他一体 ・ 萬物一体―――すなわち大調和なるものにつきて―――。 「大」 とははじめのはじめなる“一つ”なるものを言うのである。 はじめのはじめなるものとは“一つ”なるもののことであり、“一つ”なる相(すがた)こそが浄まりの極であるのである。 “一つ”なるものは、言葉にて、あるいは想念にて“無し”と言えるものを“無し”としたまことの浄まりの浄まりの消息であるのである。 神さえも生んだところの、渾べての渾べてなるもの、絶対なるもの、無限なるもの以上の渾べての渾べてなるもの、絶対の絶対なるもの、無限の無限なるものを自分の中に味わせて下さるのこそ、まことの神の愛、神の拝みにましますのである。 これが幽の幽の幽なる、無の無の無なる神および神の愛の消息にましますのである。そしてここに自分の自分なるもののよろこびなるものの消息があるのである。 ここに太陽の光線の色を楽しむとともに、太陽そのものを生んだところのもののまことの創造者としてのはじめのはじめなるもののよろこびに至る消息があるのである。 聖経『日々読誦(にちにちとくじゅ)三十章経』の中には、 「神の国の永遠の構図に於いて 神と偕(とも)に創造するの喜びを感じています。」 という、創造者として大神の経綸(けいりん)を扶翼(ふよく)する消息が歌われているのである。 風景を見に行くということは、風景を生み出しに行っているのである。 |